| 目次 (クリックで項目にジャンプし、BACKボタンで元に戻ります。) はじめに 製作方針 主要部品 回路と動作点 (Circuit Diagram) 電源回路 定電流源 製作と配線 試聴結果 おわりに August 2000 |
 |
目次
(クリックで項目にジャンプし、BACKボタンで元に戻ります。)
はじめに
製作方針
主要部品
回路と動作点
(Circuit Diagram)
電源回路
定電流源
製作と配線
試聴結果
おわりに
August 2000
MOS-FETの0dBアンプを作ってしばらく遊んだ後、次に何か作りたいと思ったのですが、これというものが見つからなくて間があいてしまったのですが、ちょうど真空管が割れて永らく置いたままになっていた弟の古い真空管ギターアンプがあったので、中がどうなっているのか試しに開けてみることにしました。
400Vもの電圧にテスターを当てるのもびくびくもので、図書館で真空管アンプの本を借りてきたり、ネットで質問したりして、割れた真空管(6L6GC)と経年劣化が予想された電解コンデンサー類を取り替え、バイアスや位相反転段の抵抗合わせなどをしているうちに、何となく自分でも作れそうな気がしてきて、無謀にも真空管アンプにトライしてみようという気になりました。
で、どんなのを作ろうか・・・ということで、当初は実験台にしたFENDERのTwinアンプと同じ6L6のプッシュプルを考えたりしていたのですが・・・、
ある方から、「全段差動が面白いのでは・・・」というアドバイスをいただき、早速ネットで”ぺるけさん”の「6AH4−GT 全段差動プッシュプルアンプ」の回路図を拝見させいただいたところ、各段を差動で引き継ぐ明快な回路構成が印象的で、この全段差動回路を見本にさせていただくことに決めました。
真空管アンプの製作工程を一通り体験することを通じて回路を学習し、真空管の音を体感するためのお試しアンプの作成。
作成は、先の0dBアンプの例を踏襲して、とりあえずモノラルで片側を作って確認した上で本チャンを作ることにしましたが、真空管やトランスを上に乗せる必要があるため、ベニヤ板の上にというわけにはいかないので、アルミの汎用ケースを使って組み上げることにしました。
試しに作った試作バージョンですが、一応完成型にもなるので独立して取り上げています。
1.回路は、ぺるけさんの6AH4−GT 全段差動アンプを見本にさせて頂く。
2.丸ごとコピーではなく、動作点などを変更して回路を自分で設定してみる。
3.見本回路を真空管だけの構成にし、真空管のアンプの音を確認する。
4.入門キットの価格レベルを目標に、なるべく安く作る。
出力管は、”ぺるけさん”の解説から「6AH4−GTは供給が豊富で海外通販なら一本千円以下で入手可能」とあり、オーディオ雑誌(MJ無線と実験)の広告を見てみたら、国内通販の広告にペア品も掲載されていたので、GEの6AH4−GTにしました。
ドライバ管も、”ぺるけさん”の実測データのきれいな曲線が気に入ったので、Sovteckの6922(E88CC)です。
電源トランスはノグチのPMC100M(280/240/200V×2、6.3V×3)、出力トランスはプッシュプル用PMF−15P(5K−8K/8Ω)、シャーシは、リードのPS−14(160mmW×90mmH×220mmD)を使用することにし、本チャンバージョンに備えてシャーシ以外の材料は左右チャンネル分購入しました。
トランス類は1台五千円以内のものですし、6AH4−GTは1本千二百円程度、シャーシも二千円ほどで、全部合わせても入門キットの価格レベルに負けないローコストです。
全段差動 プッシュプル モノラルアンプ 試作回路図;(片チャンネル分、以下、デカップリングコンデンサ類は図から省略)注;単位表記の無い抵抗はΩ、kはキロΩ、コンデンサの"u"はμF(マイクロF)を示します。
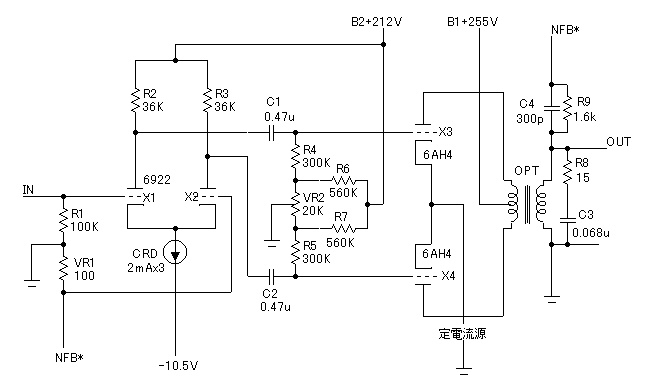
見本回路では初段が2SK30のFET(電界効果トランジスタ)になっているのですが、オール真空管構成にしようとして、最初は、これを真空管にしてドライバ段に直結しようと思ったのですが、真空管の知識レパートリーが無い私には、うまい組み合せが選べなくて、結局、FET初段を外したシンプルな2段構成にしてしまいました。
初段兼ドライバ管の6922は、同サイトにある「6DJ8/6922の特性実測データ」のSylvania製6922の特性カーブをプリントしてその上に線を色々引いてみて、見本回路よりも電流量を少し増やしたプレート電流約3mA、プレート抵抗36KΩ、バイアス3V付近で、プレート電圧が100V程度が動作起点となるロードラインとしました。 この6922のカソードの定電流源をマイナス側に引くことによりグリッドをアース電位として入力を受けるようにしています。
6AH4−GTの動作点は、出力トランスを8KΩにしたことから、”ぺるけさん”の回路解説をもとに、プレート電圧230V、プレート電流34mA、バイアス約20Vの動作点を採用し、カソードの定電流源の動作代を少し嵩上げすることも兼ねて見本回路を参考にグリッド電位を数ボルト持ち上げるプラスのバイアス調整回路を入れることにし、それらを含めて電源電圧を255Vにしています。 出力段グリッドのバイアス調整回路に流す電流はB電源から取り、調整用VRの中点で4V程度でバランスするように抵抗値を設定しました。
電源はPCM100Mの240V端子からダイオード整流し、抵抗とコンデンサーの2段フィルターを通した後にトランジスタのリップルフィルターを入れ、ダーリントン接続したトランジスタQ2(2SC2335)はシャーシ上の放熱器に取り付けています。
6922の定電流源用のマイナス電源は6.3Vのヒーター電源を倍電圧整流し、CRD(定電流ダイオード)と6Vのツエナーダイオード二本とPNPトランジスタ(2SB647)で軽く定電圧化しました。
また、何事も体験とは言え、ノイズが出たりすると対策がよくわからないのでヒーター電源は直流化し、ハムバランサーも付けることにしました。
6AH4−GT用のヒーター電源はダイオードによる電圧低下を押さえるためにショットキバリアーダイオードを使いましたが、電流量の少ない6922用は通常のブリッジダイオードを使用し、コンデンサーの前に0.8Ωの抵抗を入れて6.3Vに調整しています。
B電源(Main Electric Source);
図左=C電源(Minus Source)と、図右=ヒーター電源(Heater Source)
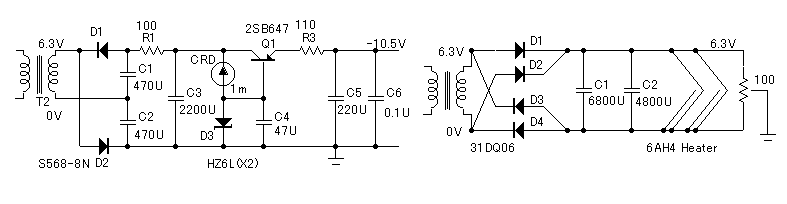
当初は、6AH4−GTの定電流源は下図左側のように、”ぺるけ”さんの見本回路と同様にトランジスタ(2SC3298)とツエナーダイオードで作り、6922の定電流源も2mAのCRDを3本並列で6mAとし、マイナス電源もヒーター電源を半波整流しただけの電源だったのですが、後日、次のような経過で変更しました。
1)CRDが定電流特性を発揮するための電圧(VP)は、当初の6.3Vのヒーター電源を半波整流した電源電圧では十分な余裕があるとは言えなかったことと、並列により等価的な抵抗値が低下することや、温度特性があまり良くないことなどから、CRDの並列をやめて、 マイナス電源を倍電圧整流に変更し動作電圧を確保するとともに上図のように定電圧化し、規準電圧ICであるTL431Cとトランジスタ2SC1815で下図中央のような定電流源に変更しました。
2)その後、”ぺるけ”さんの全段差動オフ会に出られた”kimco”さんのOPアンプ(演算増幅器)ICの定電流回路を拝見して、6AH4−GTの定電流源の方も、下図右側のように、OPアンプ=JRC JNM4558DD(ローノイズ選別品)を使ったタイプに作り直し、OPアンプ用に15Vの電源に小型トランスを追加しました。
参考;TL431を使った定電流源はトランジスタ技術スペシャルNo.1「個別半導体素子 活用法のすべて」のP44、OPアンプを使った定電流源はP134を参照しました。
図左=当初の6AH4用定電流源、変更した6922用定電流源(中央)と6AH4用OPアンプ定電流源(左)
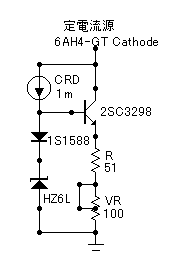 |
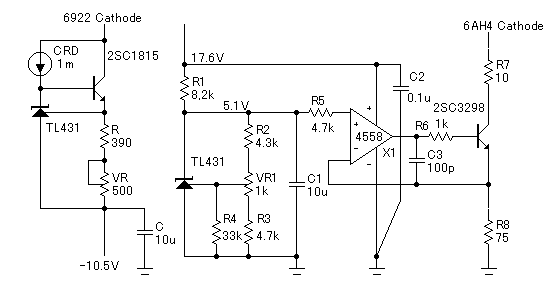 |
シャーシ上の部品の配置は、手前に真空管を並べるのが一般的なようですが、電源トランスと信号系をなるべく離したかったので、写真のように、一番手前に電源トランスを置き、トランジスタ用の放熱器、6AH4−GT、6922、出力トランスの順に並べました。
シャーシ内部は電源関係と定電流源は穴開き基板に組み、電源基板類はシャーシ壁面に取り付け、6AH4−GTの定電流源は小型の放熱器を付けて出力管ソケット近くに取り付けました。放熱器の上面にあたるシャーシには熱気を逃がすための空気穴を開けています。 また、信号ライン等は”ぺるけ”さんのコメントを参考に上下(正・逆)をできるだけ同条件にするため配線を捩って接続しなおしました。
後で色々と手を加えやすいように(というより、本チャンバージョンのためにバラしやすいようにするためもあって)、回路の機能ブロックごとに主要部分をユニバーサル基板に乗せたのですが、基板を取り付けた後の配線で、基板の端子からソケットの各ピンやラグ端子などへ空中配線したため、後で手を加える時に配線を掻き分けて作業しなければならなくなり、意図はあまり生かせない結果でした。
ゲインが小さいのとヒーターの直流化が効いたのかハムノイズらしいものも聞こえなくて、まずは一安心でした。
元々の音量が小さいので負帰還を6dBもかけられないのですが若干の増幅は得られるのでCDをパーソナルな環境で鳴らすには十分です。
小さい真空管だし、「ソフトでムーディな感じの音かな?」などと想像していたのですが、音を出してみると、これが予想外のビシッとした力感のある音です。
真空管アンプが「こんな音とは思わなかった」というのが実感です。
特徴的なのは、音離れが良いと言うか、スピーカーの周りに音がまとわり付くような感じがなく、コーンから音がスパッと飛び出してくるところです。
と、言うことで、はじめて真空管アンプの自作にトライしたにもかかわらず、作成した全段差動アンプは、何のトラブルもなく、予想外の中〜低域の力強さと、切れのある音を出してくれました。
ローコストで作れることと合わせて、全段差動を選んで正解でした。 自分だけでやっていたら普通のプッシュプルを作っていたと思いますし、6AH4−GTのような球を使うこともあり得なかったと思います。
余談ですが、簡単に作るには当初のように、初段は定電流ダイオード(CRD)を使い、出力段はトランジスタとツエナーダイオードの定電流源でいいのですが、差動の共通カソードに繋がる定電流源の音質への影響に注目して、作成後に上述のような変更を加えてみましたが、差動ティルの定電流源の定電流性能を高めると「音の立ち上りからのディーテイル感」が向上するような印象を受けました。
最後になりましたが、回路を参考にさせていただいた”ぺるけ”さん、kimcoさん、全段差動アンプを薦めていただいたDaluhmannさんに改めて、お礼申し上げます。
ご意見・ご感想はこちらへ az@poporo.ne.jp